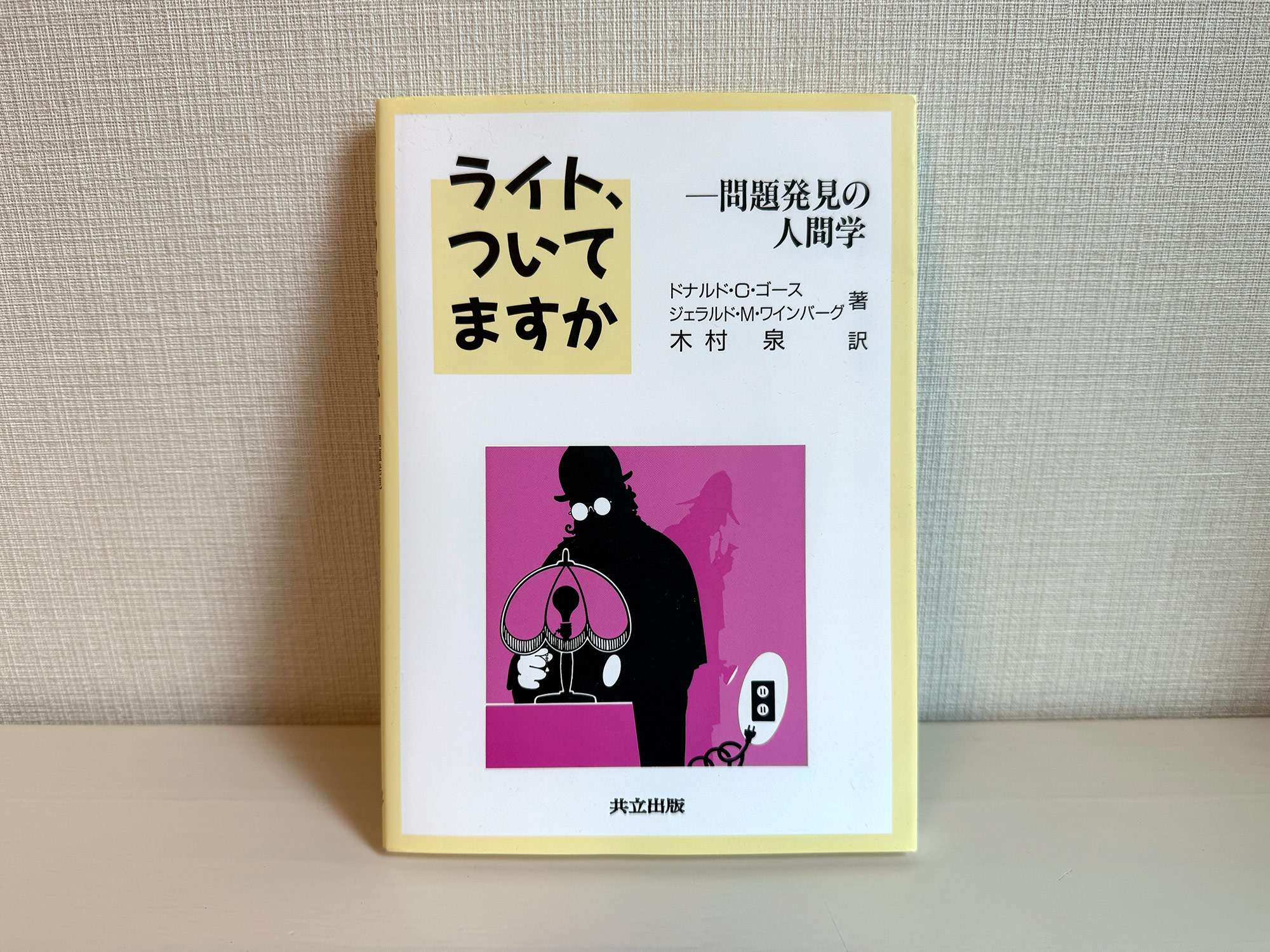書評:「ライト、ついてますかー問題発見の人間学」
問題は、解決の前に、発見されなければならない。
はじめに:この一冊が問う“問題”とは
『ライト、ついていますか?―問題発見の人間学』は、ソフトウェア開発者でありながら、心理学者、人間観察者でもあるジェラルド・M・ワインバーグが著した、問題解決に至る前段階ー「問題を発見する」という行為を徹底的に掘り下げた名著です。
一見すると技術書や組織論のようにも見えるこの本ですが、その本質は「人の思考をどう切り替えるか」という極めて汎用的なテーマにあります。特にIT業界のように「問題解決能力」が重要視される分野では、この「問題発見力」が不足していることこそが、成果物の質を左右する大きな要因となっているため、問題を発見するためには、どのような考え方・切り口で物事を捉えたらいいのか、その引き出しの多さが重要となります。
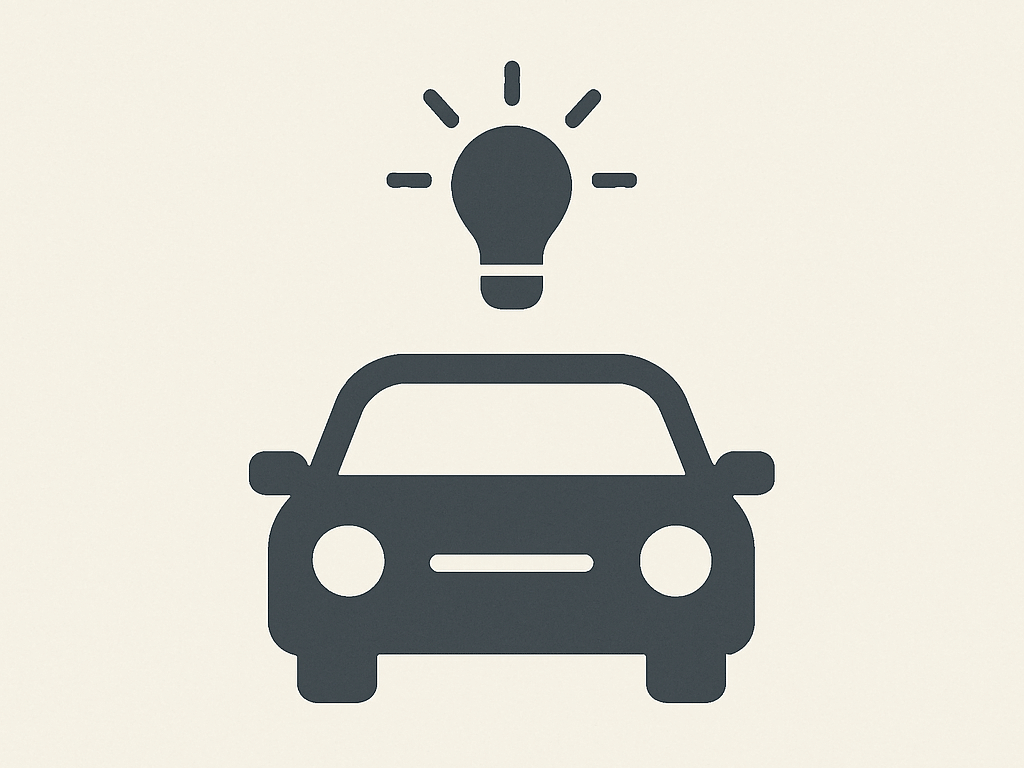
「ライト、ついてますか?」の意味とは?
タイトルにあるこの問いは、本書の第4部で登場します。
ある長いトンネルの手前に「ライトをつけてください」という標識が立てられたところ、出口でライトを消し忘れたドライバーたちのバッテリーが次々に上がってしまうという事態が発生しました。
トンネル主任技師はこの問題を解決しようと、複雑な指示文を考えますが、読み取るのに時間がかかってしまう。最終的に出した標識の文言は、たった一言:
「ライト、ついてますか?」
このシンプルな問いは、読み手の頭の中にある「ライト」を点灯させ、��自発的に考えるきっかけを与えます。
つまり、「問題を自分のものとして捉え、自分で気づくように促す」ことが、真の解決への第一歩だということを示しています。
もし人々の頭の中のライトがついているなら、
ちょっと思い出させてやる方がごちゃごちゃいうより有効である
あなたの頭の中のライト、ついていますか?
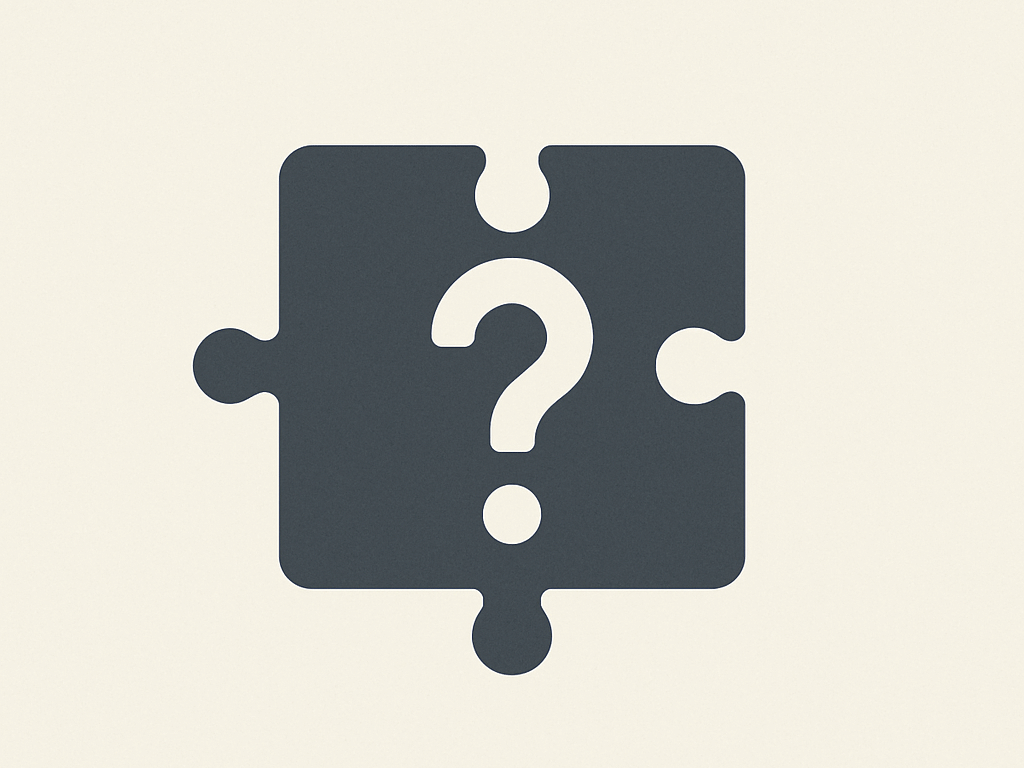
問題は“定義”次第で、解き方も変わる
第1部〜第3部では、問題とは何かを多面的に問い直しています。
-
問題は観測者によって姿を変える
→ 例:遅いエレベーター問題。乗客、オーナー、建設会社、それぞれが“問題”を違う視点で見ている。 -
解法を問題定義と勘違いしがち
→ 「こうすればいい」と言われた時、それは問題を定義したことにはなっていない場合が多い。 -
問題は、言葉の選び方ひとつで全く別のものになる
→ 問題文の書き換え実験や、言葉遊びのゴールデンリストは、IT業界の要件定義にも直結します。
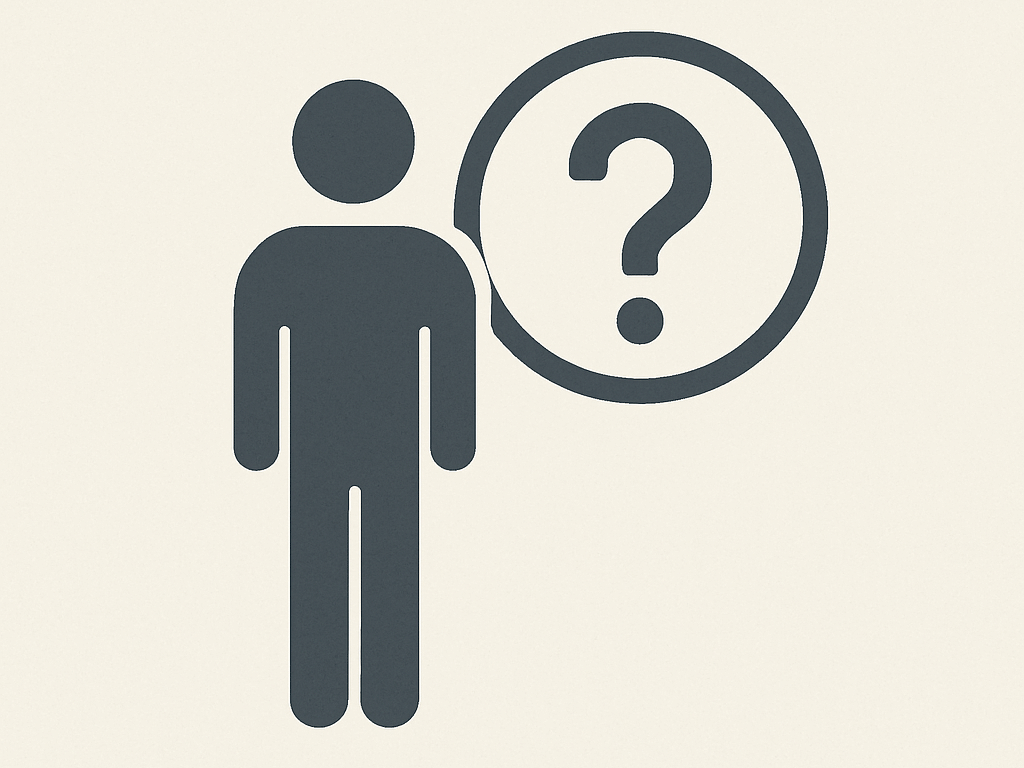
他人の問題は、誰のものか
第4部で中心となるテーマは「問題の所有者」です。
問題を誰が「自分の問題だ」と思うかによって、解決の手段も責任も変わってきます。
- 教室でのタバコ問題も、教師が問題と認識していなければ動かない。
- 駐車場不足も、学長にとって「他人ごと」であれば、何も変わらない。
この章では、「問題は自分のものとして一瞬でも捉えてみると、世界の見え方が変わる」という気づきが繰り返し提示されます。IT業界においても、「それは仕様の問題だ」「デザイナーのせいだ」といった“責任の分散”が起きやすい現場では、非常に刺さる問いでしょう。
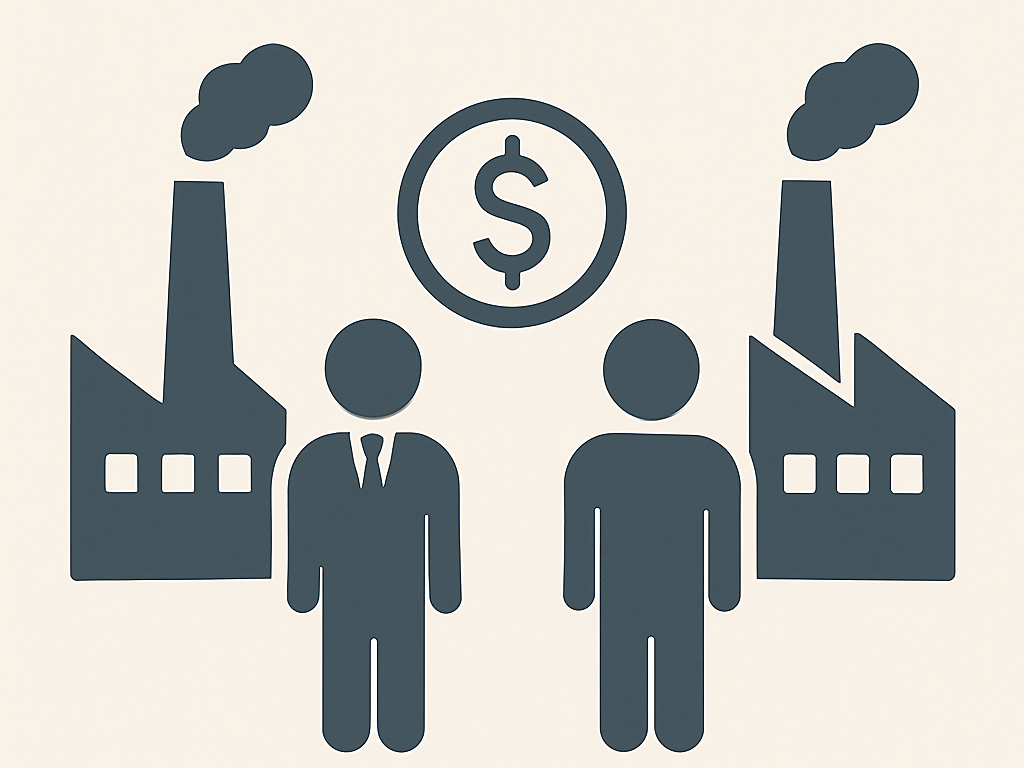
われわれはそれを本当にときたいのか?
第6部のテーマは「本当に解きたい問題」とは何かということです。
次のエピソードが一つの題材となっています。
あるおもちゃ会社が、3つの工場(西海岸・中央・東海岸)から全国の50の卸売業者におもちゃを出荷しており、そのコストを最小化したいと考えていました。
一人のエンジニアがその最適割当を計算し、中央工場からすべてを出荷すれば最もコストが安く済むと論理的に導き出す。しかし、幹部の返答はこうでした:
「それではダメだ。社長は西海岸に住んでいて、会長は東海岸に住んでいるから。」
つまり、「最小コスト化」は建前の��問題であり、真に解くべき問題は、経営陣の感情やバランスを満たすことだったのです。
- 表面上の「問題」は本当の問題ではない
- 解決しても「納得されない」ことがある
- 「何を解くべきか」を見極める力が問われている
真に解くべき問題は、クライアント自身もわかっていないことがあります。だからこそ、問題解決者は「そもそも、何が解決されるべきなのか?」を問い直す必要があります。
問題解決のスキルだけでなく、「問題の見極め」の感性が、プロフェッショナルに求められる時代です。このエピソードは、「問題処理屋」ではなく、「問題発見者」になれ、というメッセージを投げかけてきます。
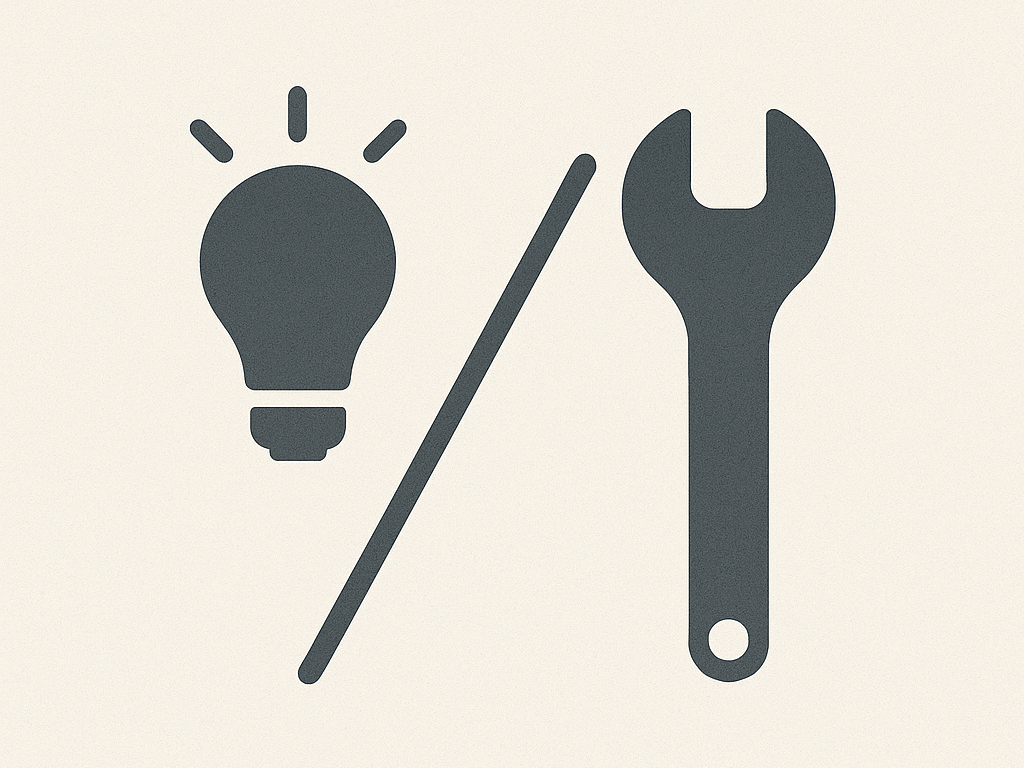
IT業界にこそ刺さる「問題発見」の技術
この本をIT業界の人々に強くすすめたい理由は以下の通りです。
-
要件定義・ユーザー視点のズレを正せる
→ 顧客が出してきた要求は、本当に解くべき問題なのかを見極めるリテラシーが身につく。 -
「技術で何でも解決できる」という罠を避けられる
→ 計算で最適解が出ても、それが必ずしも受け入れられるとは限らない。現場や組織文化との摩擦を理解できる。 -
チームマネジメントにも通じる
→ 他人の問題を奪わず、自分の問題として捉えてもらう。プロダクトオーナー、マネージャー、スクラムマスターに通じる仕事に対する姿勢を見直せる。
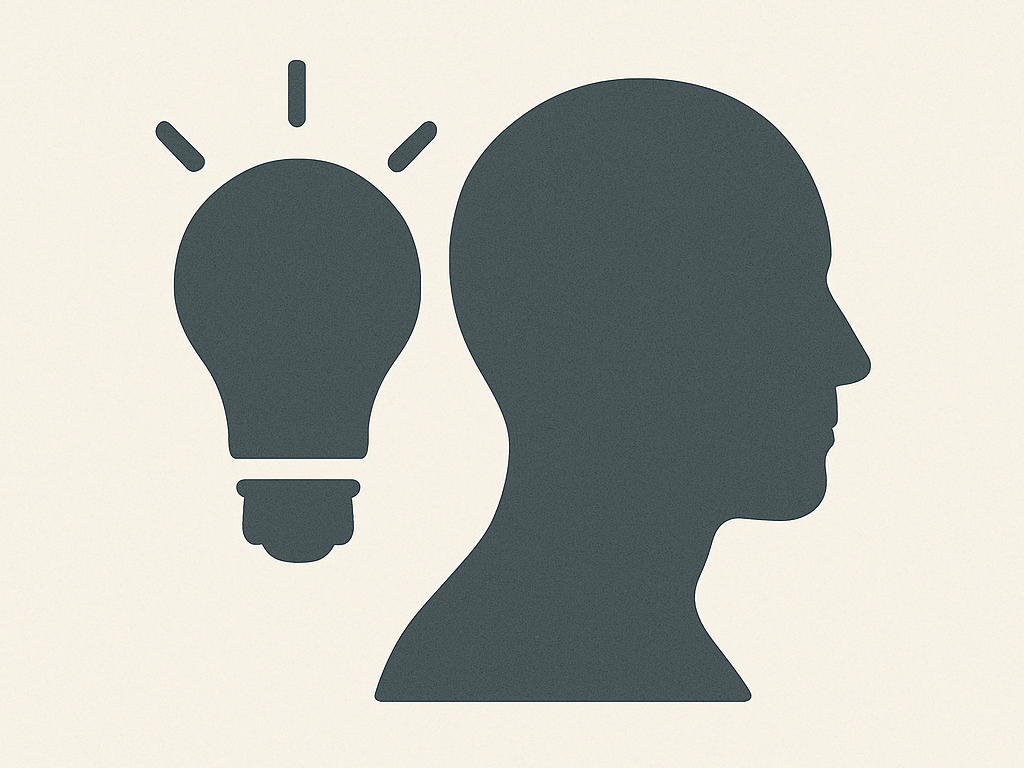
まとめ:問題とは、誰かが気づくまで存在しない
「ライト、ついてますか?」という一言は、本書全体を貫くメッセージです。
- 「その問題、本当にあなたが解くべき問題ですか?」
- 「その問題、まだ定義されていないのでは?」
- 「あなたの頭の中のライト、ちゃんと点いていますか?」
日々の仕事に追われる中で、見落としがちな「問題の本質」にそっと光を当ててくれる、それがこの一冊に詰まっています。
今回は紹介にあたり、かなりの内容を省略していますが、本記事で少しでも興味を持った方がいらっしゃったら、是非本書を読んでほしいと思います。きっと、多くの気づきが得られるはずです。